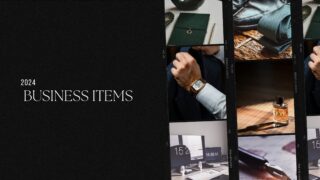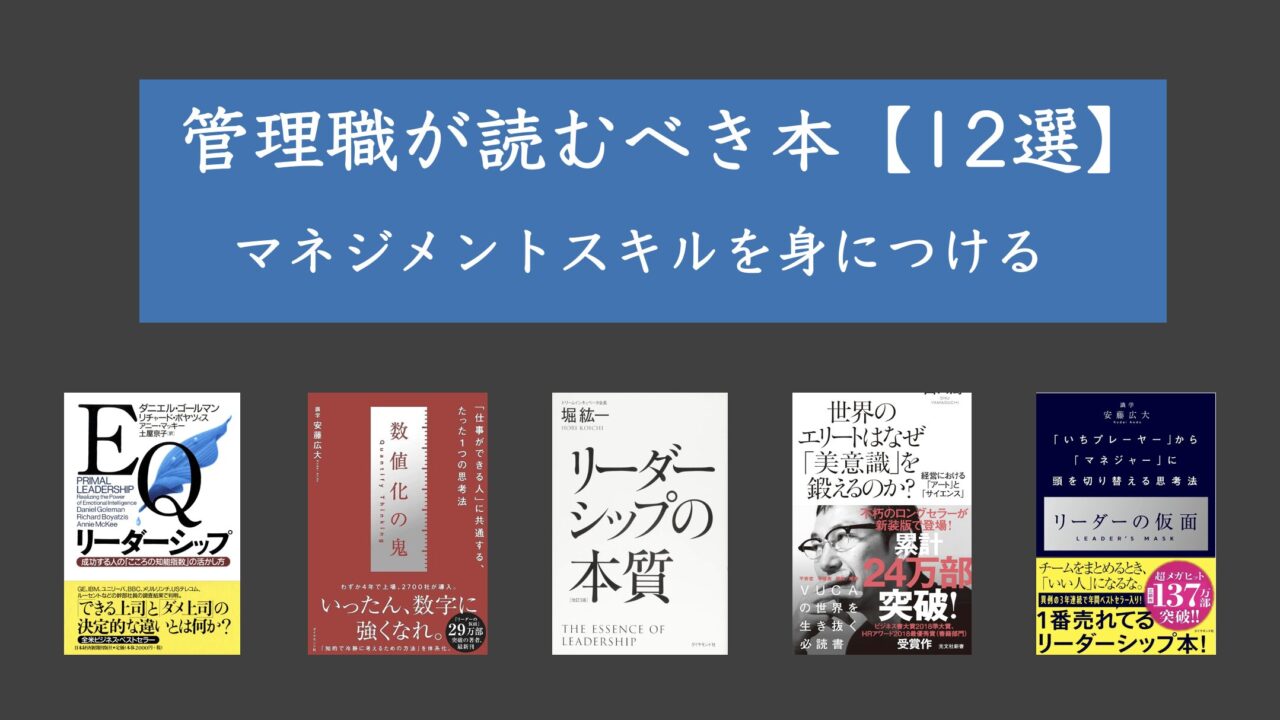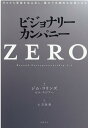新たに管理職になった、これからさらにマネジメントスキルを高めたい、どんな人にも管理職としてのキャリアを歩む上で自己成長は欠かせない要素です。
しかし、忙しい日々の中で新しい知識を身につける時間を見つけるのはなかなか大変ですね。
そこで今回は、管理職の皆さんに特におすすめの書籍12選をピックアップしました。
これらの本はリーダーシップの向上、効果的なコミュニケーション技術、チームのモチベーション管理など、マネジメントスキル全般にわたって役立つ内容が満載です。
本選びに迷っている方や、次に何を読むかを考えている方にとって非常に有益且つためになる内容ですのでぜひチェックしてください。
マネジメントー基本と原則
管理職、マネジメントと言えばこの一冊でしょう。
管理職として成功を収めるにはビジネススキルを超えた深い理解と洞察が必要です。
本書では、効果的な組織運営とリーダーシップの本質を掘り下げた管理職必読の内容が多く含まれています。
この記事では本書がどのようにしてあなたのマネジメントスキルに変革を及ぼすか詳しく解説します。
本書の重要性とその内容
本書では、あらゆるマネジャーに共通する仕事は五つであるとされています。
①目標を設定する
②組織する
③動機づけとコミュニケーションを図る
④評価測定する
⑤人材を開発する
そして、マネジメントの行う意思決定は全会一致によってなされるようなものではないとした上で対立する見解が衝突し、異なる見解が対話し、いくつかの判断のなかから選択が行われて初めて行うことができるとしています。
つまり意思決定における第一の原則は、意見の対立を見ないときには決定を行わないこと。
マネジメントにおいて非常に重要かつ本質的な内容ですね。
本書ではこのような本質的な内容が余すところなく記されています。
本書から学べる主な内容
- 組織の目標設定:明確な目標設定の重要性と、それを達成するための戦略的計画の立て方。
- 意思決定のプロセス:効果的な意思決定を行うための方法論と、それを支える情報システムの構築。
- イノベーションと起業家精神:変化を先導するイノベーションの推進と、組織内起業家精神の育成。
- 人材の開発と育成:従業員の能力を最大限に引き出し、継続的な学習と成長を促す管理技術。
管理職がこの本を読むべき理由
管理職として組織をマネジメントする際、必ず直面する問題があります。
それは、
仕事の生産性を上げるうえで必要とされること
人がいきいきと働くうえで必要とされること
この二点はまったくの別物ということです。
いくら生産性が高くても職場環境が悪い、一方でどれだけ職場環境が良くても生産性が悪く収益性に乏しい。
このどちらもマネジメントとしては失敗となります。
このように、本書では他の有名な経営に関する本のほとんどのエッセンスが記載されています。
経営哲学の原理原則を読み解き、他と圧倒的差別化を図りましょう。
”やさしいけど指示が通らない管理職”
”周囲の意見を聞かずパワーだけで組織を動かす管理職”
どちらも管理職としては…。
人を動かすのはむずかしいね…!
論語と算盤
「近代日本経済の父」と称される渋沢栄一によって書かれた歴史的名著。
時代は変わっても、ビジネスと倫理がどのように共存するかを探求した渋沢栄一が現代のリーダーたちにとっても変わらぬ価値観や倫理観を説いてくれます。
本書の重要性とその内容
著者である渋沢栄一は儒教の教えと西洋の経済理論を組み合わせ、ビジネスの成功が倫理的な基盤の上に築かれるべきであると論じました。
「富は正しい道理でなければ永続できぬ」という自らの主義に沿ったものになっていますね。
本書から学べる主な内容
- 倫理的なビジネスの基礎:「論語」の教えを現代ビジネスの実践にどのように応用できるかを示しています。
- 長期的な視点の重要性:単なる短期的な利益追求ではなく、長期的な視点を持ってビジネスを行うことの重要性を強調しています。
- リーダーシップと責任:真のリーダーは、経済的な成功を超えて社会全体の福祉に貢献する責任があると説いています。
管理職やビジネスリーダーがこの本を読むべき理由
「労使はともに儒教の教えに則り、互いに思いやらなければいけない。使用者は暴利を貪らず労働条件を整え、労働者はわがままを言わずに誠意をもって働くべきだ。」
本書に出てくる一節です。
すべてのビジネスパーソンが肝に銘じておくべき金言ですね。
管理職になると社会的地位が上がった、偉くなったと勘違いをして部下や従業員に強くあたる人も出てきます。
渋沢栄一の『論語と算盤』は、経済活動がいかにして倫理的な原則に沿って行われるべきか、そしてそれがどのようにして社会全体の利益に貢献するかを示す時代を超えた名著です。
幕末から明治維新、その後の停滞を経験した著者の金言の数々は、終戦から高度経済成長を経て現在に続く経済的停滞と非常に酷似しており、現代に生きる私たちに道筋を示してくれています。
EQリーダーシップ:成功する人のこころの知能指数の活かし方
現代のリーダーシップにおいてEQ(感情知能指数)はIQと同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。
ダニエル・ゴールマンの『EQリーダーシップ:成功する人のこころの知能指数の活かし方』は、リーダーが自身の感情知能を理解し、最大限に活用するための包括的なガイドです。
この記事では、本書がどのようにしてあなたのリーダーシップスタイルを変革するかを詳しく探ります。
本書の重要性とその内容
ダニエル・ゴールマンの『EQリーダーシップ』は、感情知能が個人の成功にどのように影響を与えるかを科学的な視点から解析しています。
ゴールマンは、自己認識、自己管理、社会的スキル、共感、関係構築の5つのキー領域に焦点を当て、これらがどのようにして効果的なリーダーシップに寄与するかを詳述しています。
本書から学べる主な内容
- 自己認識の向上:自分の感情を理解し、それがどのように行動に影響するかを知る技術。
- 感情の管理:ストレスや衝動を効果的に管理し、冷静な判断を下す方法。
- 共感の力:他者の感情を敏感に察知し、それに応じたコミュニケーションを取る能力の養成。
- 関係構築:信頼と相互尊重に基づく強固な人間関係を築くための戦略。
管理職やリーダーがこの本を読むべき理由
EQ(感情知能指数)を高めることで、仕事ではどのように活かされるのでしょうか。
それは主に以下の4つの能力につながります。
① 感情の識別:自分と他者の感情を認識する能力
② 感情の利用:ふさわしい行動を取るために感情を活用する能力
③ 感情の理解:自分や他者がそのような感情を得た原因や、その後の感情を推察する能力
④ 感情の調整:次の行動に合わせて、自分の感情を調整する能力。
いかにも管理職にとって必要なスキルですよね。
今の時代、トップダウンによる一方的な指示で組織は動かせません。
EQ(感情知能指数)を高め管理職としての能力を最大化しましょう。
リーダーの仮面
リーダーシップには見える顔と見えない顔があります。
本書では、表舞台でのカリスマだけがリーダーのすべてではないことを教えてくれます。
リーダーがどのようにして内面の葛藤と向き合い、それを乗り越えるかを掘り下げることで、真のリーダーシップについて理解を深めることができます。
本書の重要性とその内容
『リーダーの仮面』では、著者がリーダーシップの表面的な魅力だけでなく、それに隠された重圧や孤独を説明しています。
本書は、リーダーがどのように個人的な挑戦を管理し、公と私のバランスを取りながら効果的にチームを導くかの具体的な事例を提供します。
本書から学べる主な内容
- リーダーシップの内面:リーダーが直面する心理的なプレッシャーと、それをどのように乗り越えるか。
- 仮面の背後:公の場での強さと自信の背後にある、私的な不安や疑問に焦点を当てます。
- 誠実さの重要性:リーダーとしての真実性と誠実さがなぜ重要か、そしてそれをどのように維持するか。
- リーダーシップの持続可能性:長期にわたる健全なリーダーシップを維持するための戦略と実践。
管理職やビジネスリーダーがこの本を読むべき理由
本書の軸となる部分は、「プレーヤーからマネージャーへの思考の切り替え」です。
優秀なプレーヤーほど陥る現象、それは以下の二点。
・手取り足取り指導する
・部下について来させようとする
これまでは自分自身が他より多くの業務をこなせばよかったかもしれませんが、マネージャーとなった以上はチーム全員を動かさなければなりません。
手取り足取り指導をすることは一見、マネージャーとしての仕事をしているように見えがちですが、実際は指示待ち人間を量産します。
また、部下について来させようとするリーダーも同様に一見して統率力のあるマネージャーに見えがちですが、実際のところは ”その人” がいなければ組織が機能不全に陥るリスクもひめています。
「マネージャーとしての思考」を身に付けたい人は是非、本書を手にとってみてください。
リーダーシップの本質
企業目的は「生きがい(またはやりがい)」「成長」「収益」の三つ。
そのトライアングルからなる本質を、小手先のコミュニケーション術やマネジメントのハウツーではなく、人間としてリーダーはどのように組織を率いるべきか。
覚悟、態度といったリーダーシップの本質を骨太に説いた哲学的な一冊。
本書の重要性とその内容
「目的設定」「現在地の認識」「環境変化の読み」「戦略の策定」「実行」というリーダーが行うべき五つの仕事について説かれた一冊。
著者の豊富な経験をもとに、管理職としての進むべき道を示してくれています。
本書から学べる主な内容
- リーダーシップの定義:リーダーシップとは何か、そしてそれがなぜ重要なのかについての洞察。
- リーダーの資質:効果的なリーダーが持つべき核心的な資質とスキル。
- チームとの関係構築:信頼と尊敬に基づいた関係を築くための戦略。
- 決断と実行:困難な決断を下し、それを効果的に実行するための方法。
管理職やビジネスリーダーがこの本を読むべき理由
本書はリーダーシップに限らず、組織や経営についても学べるため管理職に留まらず経営の道を志したい人にもおすすめの一冊。
社長と副社長の差は、副社長と運転手の差より大きい
経験者にしか語れない言葉ですね。
仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣
効率的なリーダーシップとは、単に早く仕事を終えることではありません。
本書では、速さが高い成果とどのように関連しているか、その背後にある習慣や思考プロセスを徹底的に分析しています。
この記事では、この本がどのようにしてあなたのリーダーシップを効率的に変えるかを探ります。
本書の重要性とその内容
部長や課長ではないプレイングマネージャーのための時間術が書かれた本です。
日々の業務でなんとなく感じる効率の悪さなどが具体的な例とともに紹介されているので改善のイメージがしやすく、今日からでも活用できるメソッドが多く盛り込まれているので読みやすい一冊となっています。
本書から学べる主な内容
- 時間管理のテクニック:効率的なリーダーがどのように時間を管理し、優先順位を設定するか。
- 意思決定のスピード:迅速かつ効果的な意思決定を行うための習慣と戦略。
- チームワークの最適化:チームの生産性を最大化するためのコミュニケーションと協力の技術。
- ストレス管理:高いペースで仕事を進める中で、如何にしてストレスを管理し、バーンアウトを防ぐか。
管理職やリーダーがこの本を読むべき理由
仕事が速いリーダーを良い事例として、具体的な行動指針が書かれています。
「新人から意見を聞く」「時間をお金に」「とりあえず着手してみる」などなど
内容的に目新しさはそこまでありませんが、実践しやすい内容や失敗例も多くプレイングマネージャーにはうってつけの一冊です。
世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?
なぜ世界のトップパフォーマーたちは、美意識に注力するのでしょうか?
山口周の著書『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』は、ビジネスとアートの交差点における美の力を探求します。
この本は、美意識が如何にして個人の成功や組織の革新に寄与するかを明らかにし、それをどのようにして自身のキャリアや生活に応用するかを示します。この記事で、その魅力と価値を掘り下げます。
本書の重要性とその内容
世界のエリートが「美意識」を鍛える理由、それはこれまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた経営、いわば「サイエンス重視の意思決定」では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはできない。
冒頭部分で本書の回答が述べられており、各章では近年の企業経営者たちがなぜ美意識を磨くことを重視しているのか。その答えが明確に論理的に示されています。
本書から学べる主な内容
- 美意識の定義と重要性:美意識が個人の思考、創造性、感情にどのように影響するかの解析。
- エリートの習慣:成功したビジネスリーダーやクリエイターたちが美意識をどのように養っているかの具体例。
- 美を取り入れた問題解決:美意識を利用して複雑な問題を新しい角度から解決する方法。
- パーソナルブランディングと美意識:美意識が如何にしてパーソナルブランドを向上させ、プロフェッショナルな成功に貢献するか。
管理職やビジネスリーダーがこの本を読むべき理由
昨今、コーポレートガバナンスをはじめとして「正しくないこと」への見方、拒否反応がこれまで以上に厳しくなってきました。
その中で、意思決定のモノサシに主観的な「アート」を用いるという新たな選択肢は今後の社会を支えていく世代にとって常識となり得るケースかもしれません。
「VUCA」な社会に求められる内部変革、自らの手で進めてみませんか?
山口周さんの著書はどれも視点がすばらしいよね!
これまでの固定観念や価値観を覆す感性をひしひしと感じます!
ビジョナリーカンパニーZERO
絶え間なく変化する市場でいかにして企業は長期的な成功を保ち続けることができるのか。
ジム・コリンズとビル・ラジアーの『ビジョナリーカンパニーZERO』は、持続可能な成長と革新を達成する企業の特徴を深掘りし、その成功の秘訣を明らかにします。
本書では、この画期的な研究がどのようにビジネスリーダーの思考を変えるかを探ります。
本書の重要性とその内容
ゼロから事業を生み出し、偉大で永続的な企業になる為の考え方、方法を述べた本。
500頁と重厚な書籍となっているため、敬遠しがちな人もいると思いますが企業活動におけるファンダメンタルな原理原則は非常にシンプルで分かりやすい内容となっています。
また、
”最も大切なのは正しいビジョンよりも正しい人材である”
この一節も本質をついた素晴らしい観点だと思います。
本書から学べる主な内容
- ビジョナリーな理念の構築:企業がどのようにして強固なコアバリューを設定し、それを守りつつ進化させるか。
- 革新への取り組み:持続可能な革新を実現するための戦略とプロセス。
- リーダーシップの連続性:効果的なリーダーシップの移行が企業の長期的な成功にどのように影響するか。
- 組織の適応力:外部環境の変化に対応するための組織的な柔軟性をどのように育てるか。
ビジネスリーダーがこの本を読むべき理由
「リーダーシップとは、部下にやらなければならないことをやりたいと思わせる技術である」
本書では、この定義には重要な点が3つあるとしています。
第一に、やらなければならないことを見極めるのはリーダーの役目。
第二に、重要なのはやらなければいけないことをやらせることではなく、やりたいと思わせること。
第三に、リーダーシップとは「サイエンス(理屈)」ではなく「アート(技能)」
リーダーシップはアート
前段でご紹介した「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか?」とも重なる部分がありますね。
本書を通してビジョンとパーパスの大切さ、人をやる気にさせるリーダーシップを学び取り、自身の飛躍的成長につなげましょう。
数値化の鬼
「数字」というものに対して少しでもマイナスイメージを持っている全ビジネスマンに必ず読んでほしい一冊です。
”とにかく一旦、数字に強くなれ”
ビジネスと数字は切っても切り離せないことは誰しも分かっていますよね?
そこで数字から逃げるか、心を鬼にして数字と向き合うか。
本書を手に取り、行動を数字で語れるビジネスパーソンになりましょう。
本書の重要性とその内容
数字から逃れられない以上、数字に強くなるしかありません。
本書では数字に強くなるためのステップについて具体的に示してくれています。
①まずは行動量を増やそう
②確率を意識せず、行動力をキープしよう
③確率を上げる変数を見つけて改善しよう
④変数の中でも最も重要な変数を見つけて優先して取り組もう
⑤長期的な視点で数字を考えて、逆算し短期的な行動に落とし込もう
この流れに沿ってPDCAを高速で繰り返す。
まずは行動、早く動いた順に数字で語れるビジネスマンに近づきます。
本書から学べる主な内容
- 数値化の基本:ビジネスプロセスを数値化する基本的な方法とその重要性。
- データ駆動の意思決定:収集したデータを分析し、それに基づいて賢明な決定を下す技術。
- パフォーマンスの測定と改善:KPI(重要業績評価指標)を設定し、企業の成果を定量的に評価する方法。
- リスク管理:数値化を通じてビジネスリスクを特定し、対策を講じるプロセス。
ビジネスリーダーがこの本を読むべき理由
管理職やリーダーになると、上司への報告や部下への指示をしなければなりません。
その際に上司へ「たくさん営業訪問しました」
部下へ「もう少し頑張ろう」
こんな抽象的な伝え方ではまったく伝わりませんよね?
ロジカルに伝えられないということは、それだけ齟齬を生む可能性が高いということです。
お互いの認識を最大限共有するためにも、本書を読んで数値化の鬼となりましょう。
「本当に役立った」マネジメントの名著64冊を1冊にまとめてみた
リクルートで新規事業を急成長させるなど活躍、現在は経営者塾の主催もしている著者が23年間、年間100冊の読書から厳選した本を紹介。
本書では、著者自身の仕事、リクルートで管理職育成のために主催していた「中尾塾」、現在主催している経営者対象の新生「中尾塾」での経験を踏まえ、様々な規模・業種のマネジメントに「本当に役立つ」本を紹介・解説しています。
本書の重要性とその内容
中尾隆一郎によるこの本は、64冊のマネジメント書から最も影響力のあるアイデアと戦略を選び出し、それらを実践的な知見として提供します。
本書は、リーダーシップ、戦略、イノベーション、人材管理、生産性向上など、幅広いトピックを網羅しており、各テーマごとに具体的な教訓とアプリケーションが示されています。
本書から学べる主な内容
- リーダーシップのエッセンス:歴史上の偉大なリーダーたちの教訓を解析。
- 戦略的思考:市場での競争に勝つための戦略立案の方法。
- イノベーションと変革の管理:変化を効果的に導くための具体的なガイドライン。
- 人材の育成と動機付け:最高のパフォーマンスを引き出すためのマネジメントスキル。
- 時間と生産性の管理:時間管理技術を通じて個人とチームの生産性を最大化する方法。
ビジネスリーダーがこの本を読むべき理由
管理職となり、どの本から手をつけたら良いか迷った人はまずこの本を手に取ってみましょう。
一括りにビジネス書と言っても、数ある名著の中から齋藤孝の『不機嫌は罪である』、P・F・ドラッカーの『非営利組織の経営』など、著者の豊富な読書量から厳選された「名著64冊」に絞って紹介されています。
また、著者自身の経営塾メンバーの体験談を織り交ぜて課題に沿った提案をしてくれています。
「この課題に対してはこの一冊がおすすめ。要点はこの部分」
ここまで説明してくれていますので、本書を読むことで数十年にわたるマネジメントの知恵を短時間で学ぶことができます。
とにかく仕組み化
前段でもご紹介した話題作「リーダーの仮面」「数値化の鬼」に続く第3弾のような位置付けである一冊。
組織論にとって非常に示唆に富んだ内容となっており、リーダーやマネージャーとマネジメントを手がける人には絶対に読むべき良書です。
本書の重要性とその内容
本書の目的は「人の上に立つべき人」に向けて、仕事の型になる「仕組み化」の考え方を伝えるものです。
「仕組み化」の反対は「属人化」であり、属人化のリスクを理解した上で仕組みを構築することの重要性を考えます。
構成はこれまでの二部作同様に、各章の終わりに質問を投げ掛けるパターンなので非常に読みやすくなっています。
また、組織で働くことの重要性やそのための仕組み化の重要性を説きながら、現代社会の課題にまで言及しています。
本書から学べる主な内容
- 業務の分析と評価:どのプロセスを仕組み化すべきかを見極める方法。
- システムの設計と実装:効果的な業務プロセスを設計し、組織全体で実施する方法。
- 自動化の活用:テクノロジーを活用して日常的なタスクを自動化し、生産性を向上させる技術。
- 持続可能な改善:一度仕組み化を行った後、継続的にシステムを評価し、改善するアプローチ。
ビジネスリーダーがこの本を読むべき理由
本書を読むことで、著者が記した3部作の意味を知ることができます。
著者曰く、
マネジャーとしての実践は「リーダーの仮面」、プレーヤーとしての実践は「数値化の鬼」、最後の仕上げとして、「仕組み化」の考えを理解し、仕事に役立ててほしい。
プレーヤー時代は「数値化の鬼」、マネジャー1年目には「リーダーの仮面」を、さらに上を目指していくには「とにかく仕組み化」を、それぞれ読むことで組織のピラミッドは完成する。
帯にもある通り、
「人」は責めるな、「ルール」責めろ。
すべてのマネージャーが意識するべき教訓です。
この三部作は全ビジネスパーソンが読むべき本。
読んだ人と読んでいない人で一定の差がついてしまう。
管理職1年目の教科書―外資系マネジャーが絶対にやらない36のルール
本書は外資系企業で培われた独特のマネジメントスタイルを紹介し、新任マネージャーが陥りがちな落とし穴を避ける方法を教えてくれます。
疑問点に応じて論点がわかりやすく掲載されていますので、内容も理解しやすく実践的な学びも多く含まれています。
本書の重要性とその内容
著者の外資系企業での経験に基づいて、伝統的な日本のビジネス習慣とは異なる新しいマネジメントの原則を提唱しています。
管理職としての仕事の進め方と、リーダーとしての行動指針の両方をわかりやすく説明されていますので、まさに「管理職1年目」にはうってつけの一冊です。
本書から学べる主な内容
- 非効率な習慣の排除:マネジメントの効率を低下させる典型的な行動やプロセスを避ける方法。
- コミュニケーションの最適化:明確で効果的なコミュニケーションを実現する戦略。
- 意思決定の迅速化:迅速かつ正確な意思決定を促進するためのテクニック。
- チームの自立支援:部下の自主性と責任感を促進し、自律的なチームを構築する方法。
管理職がこの本を読むべき理由
管理職になりたての頃はどのようにして成果を上げるのか、組織を成功へと導くのか分からないことも多いと思います。
本書では組織の業務効率を高める、部下の主体性を促すなど管理職としてのノウハウが凝縮されています。
管理職になったあなたが認識しておくべき大切なこと
①管理職の役割は「チームの成果の最大化」である
②チームの成果の最大化を「生産性の高いやり方」で実行する
③あなたと部下の「価値ある人材への成長」
この三点を常に忘れず、軸を持った管理職へと成長を遂げましょう。
まとめ
本記事では、管理職にとって価値ある洞察と具体的なスキルアップのための12冊の書籍をご紹介しました。
これらの書籍は、リーダーシップの鍛錬、効果的なコミュニケーション、戦略的思考力の向上、そして部下の育成とモチベーション管理など、管理職が直面する多様な課題に対応する知識と実践的なアドバイスを提供しています。
どの書籍も管理職としてのキャリアを積極的に形成し、組織全体の成功に貢献するための貴重なリソースとなります。
一冊でも多くの書籍を一人でも多くの方に読んでいただければ幸いです。